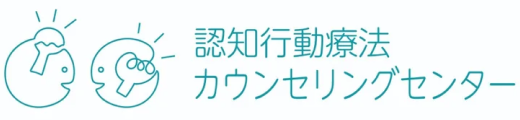2025年07月10日
- メンタルヘルス
広島でメンタル不調に早く気づくには|“部下の変化に気づく”ためのメンタルヘルス研修

こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター広島店です。
私たちは、広島市を拠点に、働く人のこころの健康を支えるカウンセリングサービスや、企業向けのメンタルヘルス研修を行っています。
この記事では、**「うつなどのメンタル不調に至る前に、職場で何ができるのか?」**という視点から、“不調の入口”に気づき、対応するための考え方や方法についてご紹介します。
■ 気づいた時には“もう限界”になる前に
「明らかに様子がおかしい」「ついに休職した」と気づいたときには、すでに状態が深刻化していたというケースは少なくありません。
しかし実際には、それ以前から**“何となく元気がない”**といった小さなサインが出ていることも多くあります。
たとえば:
- 表情が乏しくなった
- 冗談に反応しなくなった
- 仕事の進行が極端に遅くなった/早くなった
- 雑談に参加しなくなった
- 報連相が減った
こうした変化は、「たまたま疲れているだけかも」と見逃されがちですが、メンタル不調の入口として見逃してはならないポイントでもあります。
■ 心・体・行動の3つのサインに注目する
メンタルヘルスの不調は、心理面だけでなく、身体面・行動面にもさまざまな変化をもたらします。
厚労省や専門機関の資料でも、この「三側面」からの観察が推奨されています。
✅ 心のサイン(心理面)
- 落ち込みやすい、涙もろくなる
- イライラが増える
- 集中力が続かない
- 「どうせ自分なんて」といった否定的な発言が増える
✅ 体のサイン(身体面)
- 慢性的な疲労感
- 睡眠障害(寝つきが悪い、夜中に目が覚める)
- 胃痛、食欲不振、動悸など
- 肩こりや頭痛などの自律神経症状
✅ 行動のサイン(職場で見られる変化)
- 遅刻・早退・欠勤が増える
- 業務のパフォーマンスが低下する
- 報告や相談が減る
- 以前と比べて無表情・無反応になる
これらのサインは、「以前と比べてどうか」という変化の視点で見ることがポイントです。
■ ストレスチェックだけでは拾えない“日常の違和感”
ストレスチェック制度の導入が進んでいる一方で、実際の現場では、
- 「ストレスチェックはA判定だったのに、突然休職」
- 「自覚がないまま無理をしていた」
という声も多く聞かれます。
これは、質問紙ベースでは拾えない“微細な変化”が日常には存在していることを示しています。
そうしたサインに気づけるのは、毎日顔を合わせている職場の上司や同僚であることがほとんどです。
■ 管理職・人事に求められる“気づき力”とは
職場でメンタル不調の予兆に気づいたとき、最も難しいのは「声をかけるタイミング」と「言葉の選び方」です。
気を使いすぎて何も言えなかったり、逆に不用意な言葉が相手を傷つけてしまうこともあります。
こうした場面では、「何を伝えるか」だけでなく「どう伝えるか」が重要になります。
■ 声かけの例|“評価や決めつけを避ける”ことが効果的な場合も
部下や同僚に「いつもと違う」と感じた際の声かけでは、相手が話しやすい雰囲気を作ることが大切です。
特に、「大丈夫?」「うつじゃない?」といった表現は、受け手によってはプレッシャーや抵抗感を抱くことがあります。
以下は、状況に応じて参考となる声かけの一例です。
| 状況により避けたい言い方 | 配慮を含んだ声かけの例 |
| 「最近、元気ないけど大丈夫?」 | 「最近忙しそうだけど、何か手伝えることある?」 |
| 「気合で乗り切ろう!」 | 「疲れてそうだけど、無理してない?」 |
| 「うつじゃない?」 | 「調子が気になることがあったら、話だけでも聞くよ」 |
ただし、すべての人にこのような声かけが適しているわけではありません。
率直なほうが安心する方もいますし、あえて冗談を交えて接したほうが良いこともあります。
大切なのは、**その人の性格や関係性を踏まえた“柔軟な対応”**です。
■ 認知行動療法に基づいたメンタルヘルス研修のご案内
当センターでは、認知行動療法(CBT)の考え方を活かした、「不調の前段階に気づくこと」を目的としたメンタルヘルス研修を実施しています。
🔹 研修内容(一例)
- メンタル不調の三側面(心理・身体・行動)の見分け方
- 不調の“前兆”に気づく視点とは
- ストレスと行動・感情の関係
- 部下との関係性を崩さない声かけの工夫
- 実際の職場場面を想定したロールプレイと振り返り
🔹 対象となる方
- 管理職やリーダー職の方
- 人事・労務部門でメンタル対応を求められる方
- メンタル不調による離職・休職が続いている職場
オンライン・対面どちらにも対応しており、1回のみの研修から継続的なサポートまで、柔軟に対応可能です。
■ よくあるご質問(Q&A)
Q:ストレスチェックを導入しています。それだけでは不十分なのでしょうか?
A:ストレスチェックは「自分で自覚しているストレス」に限られるため、無自覚な状態や表に出にくいサインには気づけません。日常の“ちょっとした違和感”に気づく視点が別途必要です。
Q:研修は1回からでも依頼できますか?
A:はい、2時間~半日単位の単発研修も可能です。ニーズに応じて内容をカスタマイズいたします。
Q:研修後の継続的なサポートもお願いできますか?
A:月1回の「顧問心理士契約」として、定期的な職場訪問・相談対応・社内向けレポートなどを提供するプランもございます。
■ お問い合わせ・お申し込みはこちら
- Webサイト:
https://hiroshima.cbt-mental.co.jp/ - LINEでのご相談:
https://lin.ee/26sKHRK8 - お申込みフォーム:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
■ 最後に
うつ病や適応障害など、明確な診断が出てからの対応には時間も労力もかかります。
だからこそ、「不調の兆し」に早く気づく力が、職場全体の健全性を守る第一歩です。
認知行動療法カウンセリングセンター広島店では、“診断前の違和感”に対応できる職場づくりをお手伝いします。
ぜひお気軽にご相談ください。