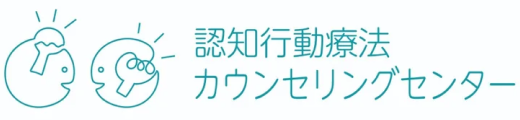2025年09月28日
- ご案内
広島の認知行動療法研修『睡眠障害へのカウンセリング』

──岡島義先生 オンラインセミナーレポート(2025年9月開催)
睡眠障害は、うつや不安、発達特性など、さまざまな心理的困りごとと深く関係しています。
日中の気分・集中力・意欲の低下が続いている場合、「まず睡眠の質を整える」ことが回復の第一歩となることも少なくありません。
しかし現場では、「眠れない」と訴える方への支援は“感覚や経験”に頼りがちで、系統的な理解や支援方法に迷いを感じる声も多く聞かれます。
こんにちは、認知行動療法カウンセリングセンター広島店です。
2025年9月27日、オンラインにて開催した専門職向けセミナー【事例で学ぶ睡眠障害への認知行動療法】には、全国から多数の心理職・支援者の皆さまにご参加いただきました。
登壇いただいたのは、睡眠支援の研究と臨床の第一線で活躍されている岡島義先生(東京家政大学 教授)。
本記事では、研修の様子や主催者としての学びを、ネタバレにならない範囲でご紹介いたします。
睡眠は“個別に支援すべきテーマ”である
研修前半では、睡眠のメカニズムや不眠症の理解、そして認知行動療法によるアプローチ(CBT-I)の枠組みが丁寧に解説されました。
岡島先生は、「睡眠は、うつや不安などの“二次的な影響”としてだけでなく、独立した支援対象として考える必要がある」と明言されました。
実際、日中の疲労や集中力の低下、意欲の減退といった症状の背後には、慢性的な不眠が存在するケースも少なくありません。
それにもかかわらず、「薬を出してもらった」「気にしすぎるのが悪い」など、睡眠が適切に支援されていない現実もあります。
本研修では、睡眠の構造(恒常性・概日リズム・覚醒系)を明確に整理し、「なぜ眠れなくなるのか」「どう介入すべきか」がロジカルに解説されました。
受講者からも、「点と点だった知識が線になった」との声が多く寄せられました。
主催者の個人的な感想:自分の睡眠も振り返った
今回の研修を通じて、理論的理解が深まっただけでなく、自分自身の生活にも目を向ける時間となりました。
「眠れないことで困っている人」はもちろん、
「そこまで深刻ではないけれど、睡眠に満足していない人」に対しても、どのように支援を届けるか。
岡島先生は、心理的柔軟性モデルや生活リズムの“偏り”といった概念を通じて、「眠れない=悪い」ではなく、「より快適に眠れる工夫」を共に考えることの大切さを教えてくださいました。
また、支援者として「まずは自分の睡眠を整えること」がどれほど重要かを、押しつけがましくなく、しかし説得力をもって伝えてくださいました。
この考え方は、支援の現場でも、自分自身の生活でも、大きなヒントになると感じました。
事例報告:臨床の“空気感”が伝わってくる
後半では、岡島先生が実際に担当されたケースの紹介がありました。
支援は、睡眠日誌による見立てからスタートし、睡眠スケジュール法やセルフモニタリングを通じて段階的に進行。
終結に向かうプロセスまで、支援者の言葉選びや関わり方が丁寧に解説されました。
印象的だったのは、「技法の適用」よりも「関係性の形成」に重きが置かれていた点です。
たとえば、睡眠記録がうまくつけられなかったクライエントに対して、
「気にかけていたこと自体がとても大切なんです」と声をかけるような、“行動を評価する姿勢”が随所に感じられました。
また、「すべてが順調に進むわけではない」現実にも触れられ、停滞期や迷いのある場面も隠さず紹介していただけたことが、より実践的な学びにつながりました。
“ユーモア”という支援技術
岡島先生の支援スタイルの中でも、特に印象的だったのがユーモアの絶妙な使い方です。
笑いを取るためでも、場を和ませるためでもなく、“自責や不安をやわらげ、その人らしさを取り戻すための技術”としてのユーモアが、随所に丁寧に仕込まれていました。
たとえば、眠れなかったことに落ち込むクライエントに対してちょっとしたユーモアを交えつつも、行動への肯定をしっかり届ける姿勢。
また、睡眠記録がうまくつけられなかったことを謝るクライエントに対しては、
「記録を取れていないことより、“取らなきゃって思ってた時間”が最高の認知行動療法ですよ」
と笑顔で返し、できなかったことを責める構造から丁寧に引き離していく。
こうしたやり取りは、単なる「優しさ」や「親しみやすさ」ではありません。
そこには、「クライエントが失敗だと思っている事を意味のあるものに変える」「評価ではなく価値に目を向ける」という、極めて高次な臨床的判断が通奏低音のように流れていました。
そして何より、クライエントの苦しさを受け止めたうえで、ほんの少し肩の力を抜けるように導く“間合い”こそが、岡島先生の支援の真骨頂ではないかと感じました。
睡眠支援の本質:眠ることが目的じゃない
CBT-Iの目的は、「眠れるようにする」ことではありません。
研修の中で岡島先生は、何度もこのように語られていました。
「睡眠が整うことで、“日中をその人らしく過ごせるようになる”ことが目的です」
睡眠時間を伸ばすことがゴールではなく、“眠れないことでできなくなっていたこと”を、取り戻すサポートをすること。
この考え方が全編を通して貫かれていたことが、今回の研修の質の高さを物語っていたと思います。
Q&Aより印象的だったやりとり
講義の最後にはQ&Aセッションが行われ、次のような内容が印象的でした。
Q:不登校やひきこもりの方で、昼夜逆転が続いているケースに睡眠支援は有効ですか?
A:
「昼夜逆転」が主訴ではなくても、ご本人が「昼間の活動がしづらい」と困っている場合は、睡眠支援が非常に有効です。
ただし、ご本人が困っていない場合に無理に介入すると関係性がこじれることもあるので、困っている感覚があるかどうかが見極めのポイントです。
Q:睡眠薬を使っている方にもCBT-Iは意味がありますか?
A:
もちろんあります。薬を否定するのではなく、「自分で調整できる感覚」を身につけてもらうのがCBT-Iの目的です。
薬を減らすことがゴールではなく、本人の納得感とコントロール感を育てることが大切です。
登壇講師のご紹介
岡島 義(おかじま いさ)先生
東京家政大学 教授(睡眠行動科学研究室)
公認心理師・臨床心理士
認知行動療法師・日本睡眠学会専門心理師・専門行動療法士
睡眠障害に対する認知行動療法(CBT)の実践と研究を専門とし、国内外で研鑽を積まれてきました。
これまでに日本行動療法学会「大熊賞」や、日本ストレス学会賞など多数の学術賞を受賞。
現在も複数の学会で理事・評議員を務め、後進育成や啓発活動にも積極的に取り組まれています。
現在アーカイブ視聴受付中!
本セミナーは、一定期間限定でアーカイブ視聴を受け付けております。
ご都合が合わなかった方や、もう一度復習したいという方は、ぜひ以下のリンクからお申し込みください。
📅 視聴申込ページ(Peatix)
👉 https://peatix.com/event/4517633/view
認知行動療法カウンセリングセンター広島店のご案内
- 住所:〒730-0853 広島県広島市中区堺町2丁目4-16 堺町Yビル402号室
- アクセス:広島電鉄 小網町駅 徒歩1分、土橋駅 徒歩3分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- LINE:https://lin.ee/26sKHRK8
- 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
- Webサイト:https://hiroshima.cbt-mental.co.jp/