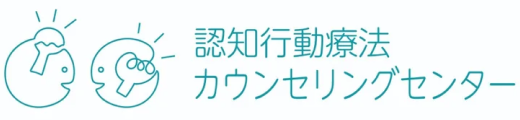2025年07月26日
- ご案内
広島の認知行動療法研修『成人期発達障害に活かす認知行動療法の技術と視点』

──金澤潤一郎先生 オンライン研修レポート(2025年7月開催)
2025年7月26日、Zoomにて開催された「成人期発達障害支援に活かす認知行動療法」セミナー。今回も全国から多くの専門職の方々にご参加いただきました。
講師は、精神科臨床・発達障害支援の両分野において長年にわたり第一線を走ってこられた 金澤潤一郎先生。その静かな語り口と、実践に根ざした知見は、今回も深い学びをもたらしてくれました。
この記事では、ネタバレにならない範囲で、研修の中で印象に残ったこと・考えさせられたことを主催者視点でご紹介します。
◆「理論」ではなく「支援者の姿勢」を語る講師
Zoom研修でありながら、画面越しに「惹きつけられる空気感」がある——それが金澤先生の講義です。
専門用語を並べたり、見せ場をつくるような派手さはありません。ただ、ひとつひとつの言葉が丁寧で、誠実で、何より“支援者としての痛み”を知っている人の言葉でした。
「良かれと思ってやったことが裏目に出る」
「指導と支援の境界が揺らぐ」
「やってはいけないと分かっていても言ってしまう」…
支援の現場では、理屈通りにはいかないことばかりです。その中で、何度も“うまくいかない”経験を重ね、それでも考え続けてきた人だからこそ語れる、重みのある内容でした。
◆「間違い指摘反射」への気づき
今回の講義で特に印象的だったのが、先生の提唱するキーワードのひとつ、**「間違い指摘反射」**です。
これは、「支援者が、目の前の“誤った行動”や“問題ある言動”を見つけると、つい指摘したくなってしまう反射的な反応」を指します。
金澤先生は、こう語りました。
「多くの支援者が『本人のために』と考えて、間違いをその場で正そうとします。しかし、それが繰り返されると、本人は“考える前に否定される”という経験を重ね、やがて“自分で考えること”そのものをやめてしまうんです」
つまり、間違いを指摘すること自体が、相手の“行動の芽”を摘んでしまっているという構造です。
私たちは時に、支援という名のもとに「矯正」「指導」を無意識にしてしまうことがあります。その行為が、“成長のため”と思っていても、実際には“萎縮と回避”を生んでいるかもしれない。
この視点は、研修参加者に大きなインパクトを与えたと感じました。
◆「間違いへの指摘」だけが問題ではない
また、指摘されていたのは 行動の間違い だけではありません。
「やり方が違う」
「そんなやり方じゃうまくいかない」
「それは前にも言ったはず」
……こうした“修正”を繰り返されると、人は徐々に「どうせやっても怒られる」「何をしてもダメなんだ」と学習してしまいます。
金澤先生は、それがいかに支援の根底を揺るがすかを、淡々と、しかし深く伝えてくださいました。
支援の本質とは、「今の状態を正すこと」ではなく、「変わろうとする試みに並走すること」である——その姿勢が改めて問われた講義でした。
◆ ゴルファーとキャディのたとえ
金澤先生がたびたび使われる、印象的なたとえ話があります。
「ゴルファー(当事者)がプレーをする人であり、キャディ(支援者)はその補佐をする人です。どんなにアドバイスをしても、最後にクラブを振るのはゴルファー。支援者が代わりに打つことはできません」
この言葉には、支援の本質が凝縮されています。
ときに支援者は「何とかしてうまくやらせたい」「代わりに打ってあげたい」と思ってしまいます。しかしそれは、“支援”ではなく“代行”であり、当事者の力を奪ってしまう危険性すらあります。
このたとえに込められたメッセージは、支援者としての立ち位置を再確認させてくれるものでした。
◆ コンパッションな関わりとは?
もう一つ、今回特に印象的だったのが、「コンパッション(思いやり)」のあり方 です。
「優しさ」「寄り添い」「受容」——こうした言葉は支援の世界でよく語られますが、金澤先生が伝えてくださったのはもっと深いものでした。
たとえば、支援者が「共感しよう」と思っても、実際にはこんな気持ちになることがあります。
- また同じ話か…と思ってしまう
- それはあなたが悪いのでは?と考えてしまう
- もう少し自分で何とかしようよ、と思ってしまう
そんな「共感できない自分」に対して、つい罪悪感を持ってしまう支援者も多いでしょう。
でも、金澤先生はこう話していました。
「“共感できない自分”を責めるのではなく、そこに気づき、“それでも関わろうとする”ことこそが、コンパッションです」
それは、感情ではなく態度の話。
“わかろうとする努力”“目の前にいる人を手放さない姿勢”——それこそが、支援者の姿勢として最も重要なのだと伝わってきました。
◆ 支援者は、試されている
このセミナーを通じて、支援とは「本人を変える技法」ではなく、「支援者自身の在り方」が問われる営みなのだと感じさせられました。
言葉を選ぶ、指摘を飲み込む、相手に任せる。
どれも簡単ではないけれど、それを日常的に“選び続けること”が支援であり、その先にあるのが信頼と成長なのでしょう。
◆ おわりに──この学びをどう生かすか
参加者の多くは、大学・病院・企業・支援機関など多様な現場で働く心理職・支援者の方々でした。研修後のチャット欄では、「気づきが多かった」「もっと早く知りたかった」といった声も寄せられました(すべてミュートでの受講ですが、後日多くの感想が届いています)。
主催者として、こうした学びの場を作るにあたって感じるのは、「届けたい内容」があっても、それをどう受け取るかは受講者の自由だということです。
「変えてやろう」と思うのではなく、「安心して学べる場を整えること」が、主催者として私たちにできる最大の役割なのだと、改めて実感しました。
そして今回はまさに、そのような場が整った時間でした。
📝 録画配信のお知らせ
金澤先生の今回のセミナーは録画配信を行います。今回参加できなかった方も、ぜひご覧ください。
📅 セミナー詳細・申込はこちら(Peatix)
https://peatix.com/event/4449707/view
📍 認知行動療法カウンセリングセンター広島店
- 住所:〒730-0853 広島県広島市中区堺町2丁目4-16 堺町Yビル402号室
- アクセス:広島電鉄 小網町駅 徒歩1分、土橋駅 徒歩3分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- LINE:https://lin.ee/26sKHRK8
- 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
- Webサイト:https://hiroshima.cbt-mental.co.jp/
——登壇者情報——
金澤 潤一郎
北海道医療大学 心理科学部 准教授
成人期の発達障害、特にADHD(注意欠如・多動症)に対する認知行動療法を専門とされ、多くの臨床・研究実績をお持ちの先生です。著書には『ADHDに対する精神療法の考え方』(成人期ADHD診療ガイドブック収載)などがあり、2012年には「第1回アジアADHD学会(ソウル)」にてPoster Abstract Awardを受賞されています。
一覧に戻る