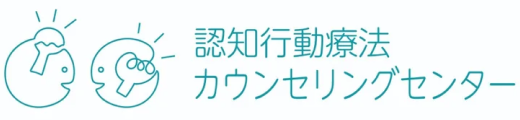2025年07月30日
- 認知行動療法
広島の養護教諭に役立つ認知行動療法

こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター広島店です。
日々、保健室で子どもたちと向き合っている養護教諭の先生方。
「いつも同じ子が来るけれど、どう関わればいいんだろう」
「体調不良の背景に、何か心の問題があるのでは…?」
「保護者とのやり取りが難しい…もっと良い伝え方はないかな?」
そんな場面に直面することはありませんか?
本記事では、養護教諭の先生方に向けて、学校現場での支援にすぐに活かせる「認知行動療法(CBT)」の視点と技法をご紹介します。専門資格がなくても活用できる内容を中心にお伝えしていきます。
認知行動療法(CBT)とは?学校現場での意義
認知行動療法とは、「ある出来事をどう受け止めたか(認知)」と「そのときどう行動したか(行動)」に着目して、こころの整理と変化を支援する心理療法です。
たとえば…
【状況】テスト前になると頭痛を訴える生徒
【認知】「失敗したら怒られるかも」「バカにされる」
【行動】保健室に避難する・欠席する
このように、出来事そのものではなく「意味づけ(認知)」が感情や行動に影響を与えているというのがCBTの基本的な考え方です。
学校現場では、体調不良や不登校、保健室登校、情緒不安定、家庭トラブルなどの背景にこうした“こころのパターン”が隠れていることが少なくありません。
養護教諭が取り入れやすいCBTの基本ステップ
CBT(認知行動療法)は、医療機関や専門家だけのものではありません。日常的な面談の中で実践可能な「問い方」「聴き方」が多く含まれており、以下の3ステップを意識するだけでも支援の質が変わっていきます。
1.気持ちや体の反応を整理する
まずは、相手がそのときどんな感情や身体の反応を体験していたかに目を向けます。
- 「どんな気持ちだった?」
- 「体のどこが反応してた?」
- 「それって、どんなふうに考えてたからだと思う?」
このような問いかけによって、本人が自分の状態に意識を向け、整理するきっかけが生まれます。
🔸 例:
生徒「お腹が痛くなって教室に行けませんでした」
先生「そのとき、どんな気持ちがあったのかな?」
生徒「また失敗するかもって思って、不安でした」
先生「“失敗するかも”って思ってたんだね。そう思うと不安になるのは自然なことだよね」
2.行動の「意味」に目を向ける
「問題行動」と捉えられる言動にも、子どもなりの“理由”や“役割”があります。
たとえば:
- 保健室に来ることで安心している
- 泣くことで気持ちを落ち着かせようとしている
これらの行動は、短期的には機能しているものの、長期的には自立や回復の妨げになる場合もあります。
ここでは「なぜそうしているのか?」を理解する視点が重要です。
🔸 例:
生徒「また保健室に来ちゃいました」
先生「そっか、来てくれたんだね。教室にいるのがしんどかったのかな?」
生徒「はい。怒られそうで怖くて……」
先生「そう思うと、ここに来ることでちょっと安心できたのかな?」
3.別の選択肢を“試す”提案
最後に大切なのは、「どう変えるか」ではなく「他の方法もあると知る」ことです。
- 「じゃあ、他にどんなやり方があるかな?」
- 「もし同じ場面が来たら、どんなふうにしてみたい?」
- 「これまでと違うやり方、ちょっとだけ試してみようか?」
この問いかけが、“選べる力”を育てる第一歩になります。
🔸 例:
生徒「また怒られるのが怖いです」
先生「怒られるの、ほんと怖いよね。でも、もしちょっとだけ違う反応を試してみるとしたら…どんなことができそうかな?」
生徒「…トイレで深呼吸してから教室に行く、とか…」
先生「それ、いいね。少し“間”をとる方法があると安心できるかもね」
保健室で見られる相談事例とCBT的アプローチ
◆架空事例1:毎朝お腹が痛くなる生徒
- 【認知】「今日も失敗しそう」「また注意されるかも」
- 【行動】登校時間になると保健室へ避難
- 【支援】
- その場の気分や身体反応を確認し、図で一緒に整理
- 「今日もちゃんと来たね」と行動へのコンプリメント
- 「1時間目だけ行ってみる」など小さな目標を一緒に設定
- その場の気分や身体反応を確認し、図で一緒に整理
◆架空事例2:友達関係に悩む生徒
- 【認知】「無視されている気がする」
- 【行動】休み時間になるとトイレにこもる
- 【支援】
- 実際に言われたこと・されたことと、感じたことを区別して話す
- 他の人ならどう考える?という視点を紹介する
- 「昨日は誰としゃべれた?」「そのときはどんな気持ちだった?」と例外を一緒に探す
- 実際に言われたこと・されたことと、感じたことを区別して話す
保護者対応におけるCBTの視点
養護教諭の先生方が保護者対応を行う場面では、子どもへの心配が強くなるあまり、時に先生への要望が強く表れることもあります。
そのような場面では、まず保護者の「感情」だけでなく、その背景にある「思考」や「信念」に目を向けてみましょう。
たとえば…
- 「この子はちゃんと見ていないと崩れてしまう」
- 「学校がもっと関わってくれていたら、こんなことにはならなかった」
こうした認知(受け止め方)の背景には、「何とかしてあげたい」「自分のせいかもしれない」という保護者なりの不安や責任感が存在していることも少なくありません。
CBT的な関わりとしては、
- 事実と感情を整理して伝える
- 子どもができていることにも焦点を当てる
- できることを一緒に考える「協働」のスタンスを大切にする
といった工夫が効果的です。
たとえば、
「●●さんが不安に感じていらっしゃるお気持ちはよくわかります。私たちとしては、□□という場面ではお子さんが前向きに取り組まれていることも見受けられました。一緒にできる対応を考えていければと思います」
と伝えるだけでも、保護者の緊張がほぐれ、対話の糸口が生まれることがあります。
『こころの整理ツール』の活用法
当センターでは、養護教諭の先生方が現場で使いやすいように、以下のようなツールをご用意しています。
📌 整理シート
- 出来事・気分・認知・身体反応・行動を記入できる用紙
- 書くことで本人も客観的にふり返ることができる
📌 子どもによくある“考え方のクセ”一覧
- 「全か無か思考」「過度な一般化」「先読みしすぎる」など
- 保護者への説明や、本人とのやり取りに活用できる
📌 自分に優しくなるための練習帳
- 自己否定感の強い子に、自分を励ます言葉や安心できる行動を見つけてもらう
保健室の引き出しに1枚入れておくだけで、関わり方の幅が広がります。
CBTによって養護教諭に起こる変化(研究紹介)
筑波大学の庄司(2012)の研究では、CBTを学んだ養護教諭が、生徒対応に自信を持ち、対応レパートリーが増えたと報告されています。
特に、
- 問いかけを工夫することで生徒が「自分の気持ち」に気づく
- 気づきに基づいて、「試してみよう」と行動に移す
- 保護者対応にも“構造的な説明”ができるようになり、対立を防げる
など、実践的な効果が多数確認されています。
よくある質問(Q&A)
Q1.心理士ではなくても、認知行動療法はできますか?
はい、可能です。
“専門的な治療介入”は心理士の領域ですが、「気づき支援」や「行動の整理」といった基本的な視点は、養護教諭の先生方にも取り入れていただけます。
Q2.子どもが気持ちを言葉にできない場合は?
気分リストや身体反応リスト、整理シートの使用が効果的です。
「言葉にできない」ではなく、「言葉にするサポート」があれば、多くの子が安心して表現できるようになります。
Q3.保護者が否定的な態度をとるとき、どうすればいいですか?
相手の“不安”に注目し、その上でできていることに焦点を当てるのがCBTの考え方です。
「こうすればうまくいくかも」という“希望の種”を一緒に探しましょう。
ご案内:当センターのサポートについて
認知行動療法カウンセリングセンター広島店では、以下のような支援を行っています。
- 教職員向けCBT研修の実施
- 個別の相談対応(事例検討含む)
- 子ども・保護者のカウンセリング対応
教育現場の「困った」に寄り添い、安心して相談できる場を提供しています。
ぜひ、学校単位でも、個人の先生でも、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ先
認知行動療法カウンセリングセンター広島店
〒730-0853
広島県広島市中区堺町2丁目4-16 堺町Yビル402号室
アクセス:広島電鉄「小網町駅」徒歩1分、「土橋駅」徒歩3分
営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
📱 LINE:https://lin.ee/26sKHRK8
📅 ご予約フォーム:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
🌐 Webサイト:https://hiroshima.cbt-mental.co.jp/