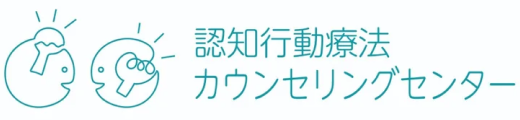2025年09月16日
- 認知行動療法
広島で適応障害へのカウンセリング

こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター広島店です。
近年、「適応障害」という診断名を耳にする機会が増えてきました。しかし、その一方で「一時的なストレス反応に過ぎないのでは」「軽い病気なのでは」と誤解されることも少なくありません。こうした捉え方は適応障害の本質を見誤るものであり、時に本人を深く傷つけることにもつながります。
本記事では、適応障害とはどのようなものかを改めて整理し、正しい理解と具体的な対処法についてご紹介します。当センターが専門とする**認知行動療法(CBT)の視点を中心に解説いたします。
適応障害とは?
「環境の変化や強いストレスにうまく対応できず、心や体に不調が出ている状態」を 適応障害 と呼びます。
発症のきっかけ
適応障害には、はっきりと確認できる原因(ストレス因)が存在します。
たとえば、
- 職場での異動や人間関係のトラブル
- 学校でのいじめや学業上のプレッシャー
- 結婚・出産・離婚などの大きな生活変化
- 家族の介護や病気、経済的な困難
などがきっかけになります。
「小さなことに弱いから」ではなく、誰でも状況次第で発症し得るのが適応障害です。
主な症状
心の反応と体の反応が同時に現れるのが特徴です。
- 心の症状:気分の落ち込み、不安、過度な心配、怒りっぽさ、やる気が出ない
- 体の症状:頭痛、胃痛、だるさ、不眠、食欲の変化、過度の飲酒など
- 行動の変化:仕事や勉強の能率低下、遅刻や欠席の増加、対人関係の回避
これらの症状は「ストレス因にさらされてから3か月以内」に現れることが多く、原因となる出来事が続いている間は症状も長引きやすいといわれています。
経過と注意点
- 環境が変わることで改善する場合もある
例えば、職場の部署異動や学校のクラス替えなどでストレス因が減ると、比較的速やかに回復することがあります。 - 放置すると長期化する場合もある
一方で、環境が変わらずに心身の負担が続くと、症状が慢性化し、うつ病や不安症に移行してしまうこともあります。
つまり、適応障害は「自然にそのうち良くなる」とは限らない病気なのです。早めにサポートを受けることが大切です。
誤解されやすい点
- うつ病と同じ病気ではありません
適応障害はPTSDや急性ストレス障害と同じく「ストレス関連障害」に分類されます。特徴は、原因となるストレス因が明確である点です。 - 誰にでも起こり得ます
性格や意思の強さとは関係なく、環境の変化や強いストレスにさらされれば、誰でも発症する可能性があります。有病率も5〜20%とされ、特別なことではありません。 - 努力不足ではありません
本人は十分に頑張っているのに、それ以上に強いストレスが続くことで症状が出てしまうのです。
適応障害の改善法
適応障害は「特別な人だけがなるもの」ではなく、誰にでも起こりうる不調です。大切なのは、放置せずに早めに適切なサポートを受けること。ここでは、当センターが行っている認知行動療法(CBT)を中心にした改善の考え方をご紹介します。
認知行動療法(CBT)の活用
認知行動療法は、適応障害の改善に有効とされる心理的アプローチです。特徴は、「症状を和らげる」だけでなく「再発予防や生活全般の安定」にもつながる点です。現状を把握した上で以下の様な取り組みを組み合わせて進めていきます。
CBTでは、以下のような取り組みを一緒に検討しながら進めていきます。
- リラクゼーション
呼吸法などを使って、強い不安や緊張を和らげる練習をします。 - ストレス因の整理
どんな状況で不調が出るのかを振り返り、自分の心身の反応を理解します。 - コミュニケーションの工夫
自分の気持ちや考えを落ち着いて伝える練習をし、周囲との関わりを改善します。 - 思考の見直し
「絶対に失敗してはいけない」「自分が悪いに違いない」といった思考パターンに気づき、より現実的で負担を減らす見方を試します。 - 日常での実践
取り組みやすい行動から新しい工夫を取り入れ、実際に効果を確かめながら進めます。
こうした流れを重ねることで、ストレスがあっても回復しやすくなり、再発を防ぐ力も育っていきます。
改善のために大切なこと
- 現状を整理する
どんな出来事が不調につながっているのか、気持ち・考え・体の反応・行動を一緒に見ていきます。 - 多方面から取り組む
考え方の工夫、行動の練習、体を休める工夫、環境の調整などを組み合わせます。 - 再発を防ぐ力をつける
今後またストレスに直面したとき、自分なりに対処できるスキルを身につけます。
医療や周囲との協力
症状が強い場合は、主治医の判断で薬を補助的に用いることもあります。薬はあくまで回復を助けるサポートであり、心理的な取り組みや環境の工夫と合わせて進めていくことが効果的です。
また、家族や学校・職場と協力し、無理のない形で生活を整えることも欠かせません。
医療や周囲との連携
症状が強い場合は、主治医の判断で薬を補助的に取り入れることもあります。薬は「改善を後押しするためのサポート」として用いられるイメージです。
また、ご本人だけでなく、家族や職場・学校との協力体制を整えることも改善を進めるうえで欠かせません。
Q&A
- Q1. 適応障害は「軽い病気」なのですか?
A. いいえ。適応障害は「ただのストレス反応」や「軽いうつ病」ではありません。PTSDや急性ストレス障害と同じく、医学的に定義された「ストレス関連障害」です。強いストレス因に直面したときに、心身にさまざまな不調が現れる正式な疾患です。 - Q2. 適応障害は本人の努力不足や性格の弱さが原因なのでしょうか?
A. そうではありません。適応障害は「適応に失敗」と表現されますが、これは本人が悪いという意味ではありません。過度に強いストレス因や環境要因が重なり、通常の対処方法だけでは乗り越えられない状態を指します。環境の影響も大きいため、決して「努力不足」ではないのです。 - Q3. どのようなサポートで改善できますか?
A. 当センターでは認知行動療法(CBT)を用いた支援を行っています。現状の反応(出来事・感情・考え・身体反応・行動)を整理し、心・行動・身体・環境といった複数の視点から改善の方法を一緒に検討します。
ご相談・お問い合わせ
認知行動療法カウンセリングセンター広島店では、適応障害に悩む方への専門的な支援を行っています。
- 住所:〒730-0853 広島県広島市中区堺町2丁目4−16 堺町Yビル402号室
- Webサイト:https://hiroshima.cbt-mental.co.jp/
- LINE:https://lin.ee/26sKHRK8
- 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
完全予約制・オンライン対応も可能です。どうぞ安心してご相談ください。
一覧に戻る