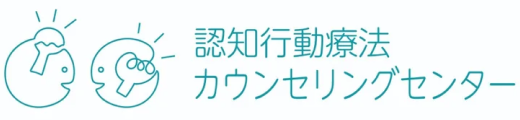2025年02月21日
- 認知行動療法
パニック症(パニック障害)改善に役立つ方法とは?広島でできるカウンセリングの活用法

パニック症は、「突然、強い不安や恐怖が押し寄せ、身体が激しく反応する」ことを特徴とするこころの困りごとです。一度でも経験すると、「また起こるのではないか」といった予期不安を感じ、特定の場所や状況を避けるようになることがあります。すると、少しずつ行動範囲が狭くなり、日常生活に影響を及ぼすこともあります。
このような状態に対処するためには、まず「パニック発作がどのように起こるのか」「予期不安が身体にどのような影響を与えるのか」を知ることが大切です。本記事では、パニック症の背景にある心と体の関係を整理しながら、少しずつできる対策についてお伝えします。
パニック症(パニック障害)とは
私たちの体には、「危険を察知すると、すぐに身を守る反応をする」という仕組みが備わっています。これを「生理的な防衛反応」と呼びます。
例えば、森の中で突然クマに出くわしたとします。このとき、心臓は激しく鼓動し、呼吸は速くなり、全身に力が入ります。これは「闘うか逃げるか(ファイト・オア・フライト)」という反応で、危険に対処するために体が準備をしているのです。
パニック発作では、この防衛反応が「本当は危険でない状況」で強く働いてしまいます。例えば、電車の中や人混みの中で、「息苦しい」「めまいがする」と感じたとき、「このまま倒れてしまうのではないか」「逃げられないのではないか」と強い不安や恐怖を抱きます。その結果、さらに心拍数が上がり、息苦しさが増し、発作が強まることがあります。
パニック発作による身体反応の例
パニック発作では、以下のような身体の反応が現れることがあります。
- 心臓の鼓動が速くなる(動悸):体が「すぐに動けるように」準備しているため。
- 息苦しさや過呼吸:酸素を多く取り込もうとするため。
- めまいやふらつき:呼吸の変化によって、体内の酸素と二酸化炭素のバランスが変化するため。
- 発汗や手足の冷え:体温調整のために血流が変化するため。
- 震えや力が入らない感覚:筋肉が一時的に緊張したり、脱力したりするため。
これらの反応は、「危険な状態だから起こっている」のではなく、「体が危険に備えようとしている」結果なのです。しかし、この身体の変化が「自分ではコントロールできない」と感じると、不安がさらに強まり、発作が続くことになります。
パニック症へのアプローチ
① 自身のパターンを整理する
まず、自分がどのような状況において予期不安を感じ対処しているのかを整理します。人によってパニック発作は異なり、苦手とする場所やそれに付随する考えや対処が異なってきますので自分自身のパニック症のパターンを整理していきます。
② 認知の検討
パニック発作が生じると対処しようがない、大変なことになる、発作は危険なものだなどさまざまな認知が不安や恐怖心をひきだしそういった危険な場所に行くことを回避するよう促してきます。まずはパニック症の状態を維持する認知を明らかにしてさまざまな角度から認知を検証します。
③ パニック症と向き合う
パニック発作に意識を向けすぎてしまうと過敏になりできないことが増えてしまいます。パニック発作を主とする身体反応や苦手とする場所に自身のペースで接近し身体反応や不安や恐怖などの感情と少しずつ向き合っていきます。例えば息苦しさに過敏な場合にはストロー呼吸などを通して息苦しさを感じてもらい、その不快な感覚と少しずつ向き合っていきます。そうすることで少しずつではありますが危険で圧倒されていた感覚が静まり落ち着いて対処できるようになります。
最後に
認知行動療法カウンセリングセンター広島店では、パニック症(パニック障害)にお悩みの方へカウンセリングを提供しています。一人ひとりの状態を整理しながら、ご自身のペースで取り組める方法を一緒に考えていきます。
「このままでは生活が制限されてしまうのでは」と感じている方も、少しずつできることを増やしていくことは可能です。私たちは、クライエントの方が「無理なくできること」から進められるようにサポートしていきます。
ご相談をご希望の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
認知行動療法カウンセリングセンター広島店
https://hiroshima.cbt-mental.co.jp/