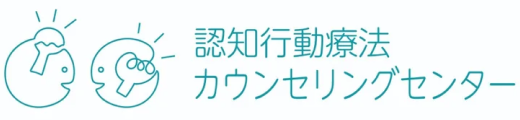2025年09月29日
- 認知行動療法
広島で嘔吐恐怖へのカウンセリング

嘔吐恐怖(エメトフォビア) は、「吐いてしまうのではないか」という強い不安や恐怖が続き、日常生活に支障をきたしてしまう状態を指します。外食や学校、職場での活動が難しくなり、人との関わりを避けるようになることもあります。本人にとって大きな苦しみとなるだけでなく、家族にとっても心配や負担につながります。
こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター広島店です。
私たちは広島市中区に拠点を置き、地域の皆さまが安心して心の悩みを相談できる場として、認知行動療法(CBT)に専門特化したカウンセリングを提供しています。
本日のテーマは 「嘔吐恐怖(エメトフォビア)」。この記事では、その特徴や背景、そして認知行動療法によるカウンセリングの方法について詳しくご紹介します。
嘔吐恐怖とは?
嘔吐恐怖とは、単に「吐きたくない」「気持ち悪いのが嫌だ」という感覚を超えて、
- 自分が吐いてしまうこと
- 他人の嘔吐を目撃すること
- 人前で嘔吐してしまうこと
を強く恐れる状態を指します。
この恐怖は、「また吐いてしまったらどうしよう」という 予期不安 と結びつきやすく、外食、電車やバスの移動、学校や会社での集まりなど、さまざまな場面を避けるようになります。結果として、学業や仕事、人間関係に深刻な影響を与えることがあります。
嘔吐恐怖に見られる特徴的な悪循環
嘔吐恐怖の方に多く見られるのは、次のような悪循環です。
- きっかけ
「少し気持ち悪いかも」という感覚や「吐いたらどうしよう」という考えが浮かぶ。 - 身体反応
不安や恐怖が高まり、動悸、発汗、喉のつかえ、胃のむかつきなどが強くなる。 - 注意の集中
体の感覚ばかりに意識が向き、「今にも吐いてしまうのでは」と考えてしまう。 - 回避行動
外食を避ける、食事中に途中退席する、体調を確認し続けるなど、「不安や恐怖を避けるための行動」をとる。 - 不安や恐怖の固定化
一時的に安心するが、長期的には「避けないと危険だ」という思い込みが強まり、不安や恐怖が悪化する。
このように、回避行動が「一時的な安心」を与える一方で、恐怖を強化してしまうのです。
認知行動療法(CBT)によるアプローチ
嘔吐恐怖へのカウンセリングでは、認知行動療法(CBT) が効果的とされています。CBTは「考え方(認知)」と「行動」に注目し、悪循環を断ち切っていく心理療法です。
1. 症状の理解と見立て
まずは、吐き気や嘔吐に関する恐怖がどのように生じ、どのような場面で強まるのかを丁寧に整理します。クライエントと一緒に「悪循環のモデル」を描き、どの場面で不安や恐怖が強まり、どの行動が不安や恐怖を維持しているかを確認します。
2. 暴露療法(エクスポージャー)
恐怖を避けるのではなく、不安や恐怖を抱えたままでも行動を続けてみる方法です。たとえば、
- 「外食の場に座ってみる」
- 「少量の食事を試してみる」
- 「吐き気を感じても、一定時間は席を立たずに過ごす」
といった段階的な取り組みを行います。
ここで大切なのは「不安や恐怖を消すこと」ではなく、「不安や恐怖があってもやりたいことをやりきれる」という体験を積むことです。繰り返し取り組むことで、「不安や恐怖があっても行動は可能」という新しい学習が積み重なり、徐々に回避せずに過ごせるようになっていきます。
3. 行動実験
行動実験では、「吐いたら必ず大変なことになる」「人に迷惑をかけてしまう」といった思い込みを、そのままにせず、実際の行動を通じて検証していきます。
たとえば、
- 「友人と軽くお茶をしてみる」
- 「外食で一口だけ料理を食べてみる」
- 「少し気分が悪い状態でも席に座り続けてみる」
といった小さな試みを行います。
その際には「本当に予想したような最悪の事態が起きるのか」「思ったほど大ごとにならないのか」を観察します。これにより、予期していた結果が実際には起こらないことを経験していきます。
4. 注意のシフト
嘔吐恐怖の方は、胃のムカつきや喉の違和感といった身体の感覚に注意が集中しやすく、その結果、不安や恐怖がどんどん高まってしまいます。そこで役立つのが「注意のシフト」です。
これは、身体感覚に縛られすぎないように、意識を別の対象へと切り替える練習です。例えば、
- 食事の場面では「料理の香りや味、温度や食感」に意識を向けてみる
- 会話の場面では「相手の話の内容や声のトーン」に耳を傾けてみる
- 移動中なら「周囲の景色や音」に注目してみる
といった具体的な方法があります。
大切なのは、「不安や恐怖を感じないように紛らわせる」のではなく、不安や恐怖があっても他のことに目を向けながら過ごせる という感覚を体験することです。注意を柔軟に切り替えられるようになると、「不安や恐怖に飲み込まれて行動できなくなる」悪循環から抜け出しやすくなります。
5. 認知のとらえ直し
嘔吐恐怖では、「吐いてしまったら終わりだ」「人前で吐いたら大変なことになる」というように、状況を非常に厳しく受け止めてしまうことが少なくありません。こうした考えは、不安や恐怖をさらに強め、行動の幅を狭めてしまいます。
そこでカウンセリングでは、実際の体験を振り返りながら「本当にそうだろうか」と別の角度から見つめ直す練習をしていきます。たとえば、
- 「これまで実際に吐いてしまった回数はどのくらいあったか?」
- 「もし吐いても、誰もそれほど気にしないのではないか?」
- 「不安や恐怖は強かったが、結局はその場にいられたこともあった」
といった視点を積み重ねていきます。
このように、「最悪の結果しか起きない」と決めつけるのではなく、「不安や恐怖があっても案外大丈夫なときがある」「思ったほど深刻にはならないこともある」という現実に気づいていくことが大切です。そうした気づきを重ねることで、不安や恐怖が強い場面でも柔軟に対応できるようになり、行動の選択肢も広がっていきます。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 嘔吐恐怖は薬で治りますか?
A. 薬で一時的に不安や恐怖を和らげることはできますが、根本的な改善には心理的なアプローチが欠かせません。当センターでは認知行動療法を中心に行い、長期的な改善を目指します。
Q2. 人前での嘔吐が怖くて学校や仕事に行けません。相談できますか?
A. はい、可能です。外出や会食に伴う不安や恐怖は嘔吐恐怖に典型的な症状の一つです。段階的に取り組むプランを一緒に作成します。
Q3. オンラインでも受けられますか?
A. はい。当センターでは全国対応のオンラインカウンセリングも実施しています。広島にお住まいでなくてもご利用いただけます。
ご利用案内
認知行動療法カウンセリングセンター広島店
- 住所:〒730-0853 広島市中区堺町2丁目4-16 堺町Yビル402号室
- アクセス:広島電鉄 小網町駅 徒歩1分、土橋駅 徒歩3分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- LINE:https://lin.ee/26sKHRK8
- 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
- Webサイト:https://hiroshima.cbt-mental.co.jp/
まとめ
嘔吐恐怖は「吐いてしまうかもしれない」という強い不安や恐怖が生活を狭めてしまうつらい症状ですが、認知行動療法によって改善が期待できます。
「もう少し自由に外食を楽しみたい」「人との交流を不安や恐怖なく持ちたい」――そんな思いをサポートするのが、私たち広島店のカウンセリングです。
嘔吐恐怖に振り回されず、自分らしい生活を取り戻す一歩を、ぜひ一緒に踏み出してみませんか。
一覧に戻る