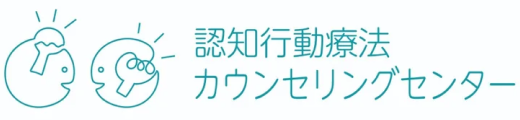2025年09月25日
- 認知行動療法
広島で強迫症へのカウンセリング

強迫症とは?生活に影響する心の症状
強迫症(強迫性障害)は、「何度も確認しないと気がすまない」「物に触れると手を何度も洗ってしまう」「頭の中で同じ考えを繰り返してしまう」といった状態が続き、生活に大きな支障をきたす心の症状です。
特徴的なのは、強い不安だけでなく、「気持ち悪い」「しっくりこない」といった不快感も原因になる点です。たとえば、左右が揃っていないことが気になって何度も並べ直したり、「完全に確認した」という感覚が得られずに同じ動作を繰り返してしまうことがあります。
決して珍しい症状ではなく、日常生活や人間関係に大きな影響を与えることもあります。
こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター広島店です。
私たちは広島市中区に拠点を構え、地域の皆さまが安心して心の悩みを相談できる場として、認知行動療法(CBT)に専門特化したカウンセリングを行っています。
この記事では、強迫症の特徴と、当センターで実施している認知行動療法に基づくカウンセリングについて詳しくご紹介します。
強迫症とは
強迫症は「強迫観念」と「強迫行為」という2つの要素から成り立っています。
- 強迫観念:しつこく浮かんできて不安や不快感をもたらす考えやイメージ
- 強迫行為:強迫観念を和らげるために繰り返してしまう行動
例えば、次のようなケースがよく見られます。
- 不潔恐怖・洗浄強迫:「汚れているのではないか」という不安や不快感から、何度も手を洗い続けてしまう。
- 確認強迫:「鍵を閉め忘れていないか」と心配になり、繰り返し確認してしまう。
- 加害恐怖:「自分が誰かを傷つけてしまったのではないか」と恐れ、行動を確認し続けてしまう。
- 不完全恐怖:「正しくできていないのでは」と思い、勉強や作業を何度もやり直す。
- 縁起強迫:「悪い言葉を見たら不幸が起こる」と考え、頭の中で“良い言葉”に置き換えないと気がすまない。
これらの症状は一時的なものではなく、日常生活を大きく妨げ、生活の質を低下させます。
強迫症の仕組み
強迫症の大きな特徴は、「やめたいのに、やめられない」という状態が続くことです。
頭では「必要ない」「意味がない」とわかっていても、実際には行動が止められず、次第に生活全体に影響が及んでいきます。
では、なぜそのようなことが起きるのでしょうか。
強迫症には、次のような仕組みがあります。
- 不安や不快な考え(強迫観念)が浮かぶ
- 強迫観念を和らげるために、確認や洗浄などの行動(強迫行為)を繰り返す
- 一時的に安心するが、次に同じ状況になると以前よりも強い不安や不快感が生じる
- 行動がどんどん増え、生活の自由が奪われていく
さらに、不安や不快感を避けようとする「回避」や、家族に確認や代行を頼む「巻き込み」が加わることで、症状がより強固になり、改善が難しくなるのです。
認知行動療法によるカウンセリング
当センターでのカウンセリングは、いきなり練習に入るのではなく、まず一緒に整理することから始めます。
- どんな考えやイメージ(強迫観念)が浮かぶのか
- そのとき、どんな行動(強迫行為や確認など)をしているのか
- 不安や不快感を避けるためにしていることや、家族に頼んでいることがあるか
これらを丁寧に言葉にすることで、「何がきっかけで不安や不快感が強まるのか」「どんな行動が症状を長引かせているのか」が整理されていきます。
そのうえで行うのが、曝露反応妨害法(ERP)です。
ERPとは、
- 曝露:不安や不快感を感じる状況にあえて近づく
- 反応妨害:安心するために繰り返していた行動(確認・洗浄など)をあえてしない
を組み合わせた方法です。
たとえば、
- 「汚いと思うものに触っても、すぐには手を洗わない」
- 「鍵を閉めたら、心配でも何度も戻らず外出を続ける」
- 「車を運転したあと、“人をひいたかも”と感じても確かめに行かない」
といった練習を、段階を追って行います。
最初は不安や不快感が強くても、“やらずに居ても大丈夫だった”経験を重ねることで、不安や不快感が自然に落ち着いていくことを体で学んでいきます。ここで大切なのは「不安や不快感をゼロにすること」ではなく、不安や不快感があっても必要な行動を選べる自分になることです。
また、練習は生活に合わせて調整します。たとえば仕事の確認で支障が出ないように範囲を区切ったり、家族に代わりに確認してもらう習慣(巻き込み)を少しずつ減らしたりします。安全を守りながら、日常生活の中で無理なく続けられる形を一緒に構築していきます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 不安や不快感が強すぎて、練習が続けられるか心配です。
A1. 無理に大きな課題に挑むのではなく、まずは小さなステップから一緒に取り組みます。
「不安や不快感をなくすこと」ではなく「不安や不快感があってもやり過ごせる経験」を積み重ねることが大切です。少しずつ慣れていくことで、自分のペースで進められます。
Q2. 強迫症は本当に良くなるのでしょうか?
A2. 改善には時間がかかることもありますが、多くの方が認知行動療法を通じて症状の軽減や生活の回復を経験されています。小さなステップから始めることが大切です。
Q3. 家族はどう関わればいいですか?
A3. 家族が過度に巻き込まれると症状が悪化する場合があります。カウンセリングを通して、適切なサポートの方法を一緒に学ぶことができます。
ご利用案内
認知行動療法カウンセリングセンター広島店
住所:〒730-0853 広島市中区堺町2丁目4-16 堺町Yビル402号室
アクセス:広島電鉄 小網町駅 徒歩1分、土橋駅 徒歩3分
営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- LINE:https://lin.ee/26sKHRK8
- 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
- Webサイト:https://hiroshima.cbt-mental.co.jp/
まとめ
強迫症は「分かっていてもやめられない」ことが特徴で、本人にとって非常につらい状態です。しかし、認知行動療法を通じて少しずつ行動のパターンを変えていくことで、不安や不快感に振り回されない生活を取り戻すことが可能です。
広島で強迫症に悩んでいる方は、ぜひ当センターにご相談ください。
一覧に戻る