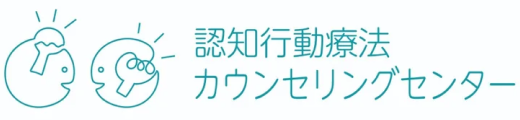2025年08月29日
- 認知行動療法
広島で過敏性腸症候群へのカウンセリング

こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター広島店です。
「外出先で突然お腹が痛くならないか不安になる」
「会議や人前で緊張すると下痢が出やすい」
「病院では異常がないと言われたのに症状が続く」
こうしたつらさを抱えている方は、過敏性腸症候群(IBS: Irritable Bowel Syndrome)の可能性があります。
IBSは命にかかわる病気ではありませんが、生活の質(QOL)に大きく影響を及ぼし、日常や仕事に支障をきたすことがあります。当センターでは、医療機関ではカバーしきれない「こころと体の関係」に注目し、心理的支援を行っています。
本記事では、IBSの基礎知識と認知行動療法(CBT)を用いたカウンセリングの進め方をご紹介します。
過敏性腸症候群(IBS)とは?
IBSは、腸に器質的な異常がないにもかかわらず、腹痛や下痢・便秘などの便通異常が慢性的に続く症候群です。推定有病率は人口の約10%とされ、誰にでも起こり得る身近な不調です。
主なタイプ
- 下痢型(IBS-D):急な便意や水様便が多い
- 便秘型(IBS-C):排便困難や便秘が長く続く
- 混合型(IBS-M):下痢と便秘を繰り返す
- 分類不能型(IBS-U):明確な分類ができないが症状が続く
過敏性腸症候群(IBS)の診断には、国際的に共通のルールがあります。
そのひとつが「ROME(ローマ)基準」と呼ばれるもので、世界中の医師が使っている診断の目安です。最新版のROME IV基準では、
「直近3か月のうち、週に1日以上の腹痛が繰り返し起こり、それが排便や便の形・頻度の変化と関係していること」がIBSの中心的な特徴とされています。
心と体のつながり ― 脳腸相関
IBSの症状は腸の過敏さだけでなく、不安やストレス、緊張など心理的要因によって強まることが知られています。
例えば、
- 電車やバスなどトイレがすぐに使えない場面で不安になる
- 会議や試験の前に腹痛が生じる
- 一度不調を経験した場所を避けるようになる
こうした悪循環は「脳腸相関(brain-gut axis)」と呼ばれる仕組みで説明されます。脳と腸は互いに情報をやり取りしており、ストレスは腸の運動に影響し、腸の不調がまた不安を呼び起こすのです。
認知行動療法(CBT)とは?
認知行動療法(CBT)は、「考え方」「感情」「体の反応」「行動」が互いに影響し合っていることに注目し、より過ごしやすい方向へ調整していく心理療法です。
IBSの方へのカウンセリングでは、特に次の3つのポイントを大切にしています。
1. 考え方のくせに気づき、整理する
IBSの方は「また体調が悪くなるかもしれない」といった不安が強くなりやすく、それが緊張や身体症状をさらに高めてしまうことがあります。
そんなときに浮かぶ「自分には無理だ」「人に迷惑をかけるかもしれない」といった考えを、一緒に見直していきます。否定するのではなく、もう少し柔らかい見方を育てることを目指します。
2. 自分のペースで新しい体験をつくる
避けてきた状況にすぐ戻ることを求めるのではなく、安心できる範囲から少しずつステップを設けながら挑戦していきます。
「無理をしないで、少しずつ安心できる場面を増やす」ことを一緒に考え、行動の幅を広げていきます。
3. 身体への意識の向け方を調整する
IBSの症状は腹部の違和感など身体感覚に関するものが中心です。そのため、体の反応に「敏感になりすぎない」ことが大切です。
呼吸法やリラックスの工夫を取り入れ、身体を落ち着ける方法を練習しながら、日々の負担を軽くしていきます。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 病院で「異常なし」と言われました。カウンセリングは意味がありますか?
A1. 医学的に異常がなくても生活に影響が出る場合、心理的支援は有効です。考え方や体との向き合い方を整えることで、不安が和らぎ生活が楽になる方も多いです。
Q2. 症状が強く通うのが不安です。オンライン対応は可能ですか?
A2. はい。当センターでは全国対応のオンラインカウンセリングを行っています。広島市外や県外の方も安心してご利用いただけます。
Q3. CBTはどれくらいの期間通えばよいですか?
A3. 目安は数か月程度ですが、症状や目標によって異なります。初回面談で一緒に無理のないペースを決めます。
「安心して過ごせる毎日」を目指して
IBSは外からは分かりにくく、理解されにくい症状です。しかし、認知行動療法を通じて「不安に振り回されない暮らし」を取り戻すことは可能です。
「また外出を楽しめるようになりたい」「人前でも安心して過ごしたい」——その思いに寄り添いながら、当センターはサポートいたします。
どうぞ、ひとりで抱え込まずにご相談ください。
認知行動療法カウンセリングセンター広島店
- 住所:〒730-0853 広島市中区堺町2丁目4-16 堺町Yビル402号室
- アクセス:広島電鉄 小網町駅 徒歩1分、土橋駅 徒歩3分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- LINE相談・予約:https://lin.ee/26sKHRK8
- 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
- 公式サイト:https://hiroshima.cbt-mental.co.jp/