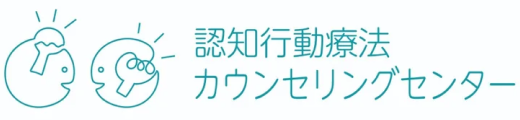2025年10月05日
- 認知行動療法
広島で不安に悩む方へ ― 不安と共に生きるためのカウンセリング

「不安で眠れない」「人前に出ると動悸が止まらない」「頭の中で“失敗したらどうしよう”という声が繰り返し響く」――そんな悩みを抱えていませんか?
不安は誰にでもある自然な感情ですが、強く続くと生活を縛り、やりたいことができなくなってしまいます。
しかし、不安は決して「なくさなければならないもの」ではありません。むしろ、不安とどのように付き合うかが大切です。
こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター広島店です。
本日は認知行動療法(CBT)の視点をもとに、不安との付き合い方をご紹介します。
不安は「自分を守るシステム」
不安を感じると、多くの人は「こんな気持ちは邪魔だ」「早くなくしたい」と思うものです。
しかし、不安は決して悪者ではありません。もともと人間に備わっている「危険を回避するためのブレーキ機能」なのです。
例えば、昔の時代を想像してみてください。森の中で生活していた人々にとって、「あの茂みの中に何かいるかもしれない」と不安を感じることは、身を守るためにとても重要でした。不安があるからこそ「近づくのはやめておこう」と警戒でき、生き延びることにつながったのです。
現代でも同じです。
「失敗するかもしれない」「嫌われるかもしれない」と未来を予測する力は、私たちがリスクを避けるためのセキュリティシステムです。たとえば、
- 「車が来るかもしれない」と不安になるから、横断歩道を確認する
- 「試験に落ちるかもしれない」と不安になるから、勉強に取り組む
- 「体調を崩すかもしれない」と不安になるから、休息を取る
このように、不安は本来「安全を確保し、準備や工夫を促す力」なのです。
しかし、このブレーキが過剰に働くと、必要な挑戦や日常の行動まで止めてしまいます。
たとえば、
- 「失敗するかもしれない」と考えすぎて挑戦を避ける
- 「嫌われるかもしれない」と思って人間関係を遠ざける
- 「体調を崩すかもしれない」と過剰に心配して外出できない
こうした状態が続くと、かえって生活の自由が奪われてしまいます。これが、不安に振り回されている状態です。
不安を「キャラクター」として捉える
不安を相手にするとき、多くの人は「怖い」「厄介だ」と感じます。頭の中で繰り返し浮かんでくる否定的な言葉に、心も体も振り回されてしまうことがあります。そんなときに役立つ工夫のひとつが、不安を「キャラクター化」することです。
キャラクター化とは、不安を単なる感情として抱え込むのではなく、「自分の隣でしゃべり続ける小さな存在」としてイメージすることです。たとえば、いつも横から口を挟んでくるキャラクターを想像してみてください。
- 「きっと失敗するぞ」
- 「恥をかくに違いない」
- 「嫌われるかもしれない」
このように、耳元でネガティブな言葉をささやき続ける存在として不安を描きます。すると「これは自分そのものではなく、不安というキャラクターの声なんだ」と切り離して考えることができるのです。
実際にカウンセリングでも、不安を「名前をつけたキャラクター」として扱うことで、不安との距離をとりやすくなります。たとえば、イラストにしてみたり、日記に「今日も○○(キャラクター名)がこんなことを言ってきた」と書いてみたりする。そうすることで、不安が“自分の中に絶対的にあるもの”ではなく、“一緒にいるけれど、選んで聞くこともできる声”へと変わっていきます。
この距離感を持つことはとても重要です。不安を完全に消そうとすると、かえって強く意識してしまいますが、「自分の中にいるキャラクターの声」として捉えると、振り回されにくくなります。そして「今日は聞き流してみよう」「ちょっとだけ意見を参考にしよう」と柔軟に関われるようになるのです。。
不安は「なくす」ものではなく「一緒に歩く」もの
多くの方が「不安を完全に消すこと」を目標にしてしまいます。
「不安があるからできない」「不安がなくなれば行動できるはずだ」と考えてしまうのです。
しかし、現実には不安をゼロにすることはほとんどできません。
大切なのは、不安を抱えたままでも行動できるようになることです。
言い換えれば、「不安と一緒に歩く力」を身につけることです。
不安と一緒に行動するとは?
たとえば会議で「発言したら笑われるかもしれない」と強い不安を感じることがあります。
そこで避けて黙ってしまえば一時的に安心は得られますが、「やっぱり自分は発言できない」という思い込みが強まり、不安はさらに大きくなっていきます。
一方で、不安を感じながらも「一言だけ言ってみる」とどうでしょうか。
緊張しながら発言してみると、意外と相手に受け止めてもらえたり、思ったほど否定されなかったりすることが多いのです。
この「不安があったけど行動できた」という体験が積み重なると、不安の声に振り回されにくくなっていきます。
不安は消えなくても人生は動かせる
不安をなくすことに全力を注ぐと、かえって「不安がある=自分はダメだ」と思い込み、行動の幅が狭まります。
しかし、「不安はあって当然。あっても進める」と理解すると、人生の選択肢は広がっていきます。
不安を抱えたまま行動することは簡単ではありません。ですが、小さな一歩を繰り返すうちに「不安があってもできた」という実感が増え、それが次の挑戦への力になります。
認知行動療法は、この「不安と共に歩む力」を少しずつ積み重ねるための方法なのです。
不安と「いい関係」を築く
不安をなくすのではなく、相談相手のように扱うこともできます。
不安の声と、もう一方の「楽観的な声(のび太のような存在)」の両方を聞き、最終的に自分が選ぶのです。
どちらの声も大切にしつつ、状況に応じて「今回は不安の声に従おう」「今回は挑戦してみよう」と選択する。
このバランスを身につけると、不安は人生の妨げではなく、むしろ安全を守りながら進むためのパートナーになります。
認知行動療法での具体的なステップ
① 現状理解(アセスメント)
最初に行うのは「いま何が起きているのか」を事実ベースで整理することです。
- どんな場面で不安を感じたか(状況)
- その時に体に出た反応(動悸、汗、震えなど)
- 頭に浮かんだ考え(認知)
- 実際にとった行動(回避した/黙った/逃げた 等)
これをシートや記録に残すことで、「不安の正体」がぼんやりした霧のようなものから、観察可能な現象に変わります。
② 心理教育
現状を整理したら、不安そのものの仕組みを知ります。
「不安=悪者」ではなく「危険から守るブレーキ機能」という理解を持つことで、不安の存在に過剰に振り回されにくくなります。
- 不安はゼロにできないが、過剰に働くと生活を妨げる
- なくそうとするより、「不安と一緒にいても動ける」が大切
この理解が、次のステップで実際に行動にチャレンジするための土台になります。
③ 不安への介入
次に、「不安に対して、どんな手を打つか」を現状や希望に合わせて考えて、取り組んでいきます。代表的なものは次の2つです。
▸ 認知再構成(考え方を整理する)
「絶対に失敗する」「嫌われるに違いない」といった極端な思い込みにとらわれず、違う角度からの見方を探していきます。
たとえば、
- 「失敗したら終わりだ」 → 「失敗しても学びになるし、やり直せる」
- 「誰からも好かれなければならない」 → 「大事なのは信頼できる一部の人との関係」
こうした視点の切り替えによって、不安の強さが少しずつ和らぎ、行動の選択肢が広がります。
▸ エクスポージャー(曝露)
避けてきた場面に、段階を追って取り組む方法です。
目的は「不安をなくす」ことではなく、「不安があっても行動できる」体験を積むことです。
- 会議で一度だけ短く発言してみる
- 電車に一駅だけ乗ってみる
- 人にちょっとしたお願いをしてみる
「不安があっても行動できた」という体験を積むことで、不安に縛られにくくなっていきます。
Q&A ― よくあるご相談
Q1. 不安は完全に消えるのでしょうか?
A. 完全に消すことは難しいですが、「不安と共に行動できる」ようになることは可能です。むしろ不安は人生に必要なブレーキでもあります。
Q2. 薬を飲んでいますが、カウンセリングを受けられますか?
A. 主治医の許可が必要ですが、併用可能です。
Q3. 初めてなので不安です。どんな流れになりますか?
A. 初回は丁寧な聞き取りから始めます。生活状況や困りごとを整理し、無理のない範囲で一緒に方法を考えていきます。
広島店のご案内
- 住所:〒730-0853 広島県広島市中区堺町2丁目4-16 堺町Yビル402号室
- アクセス:広島電鉄 小網町駅 徒歩1分、土橋駅 徒歩3分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- LINE: https://lin.ee/26sKHRK8
- 予約フォーム: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
- Webサイト: https://hiroshima.cbt-mental.co.jp/
まとめ
不安は「なくすべき敵」ではなく、「共に歩む相棒」のような存在です。
不安の声を聞きながらも、自分で選択し、自分らしい行動を積み重ねることで、人生は大きく変わっていきます。
広島で「不安に振り回されてつらい」と感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
私たちは、あなたが「不安と共に前へ進む力」を取り戻すお手伝いをいたします。